子どもの喉に魚の骨が刺さったかもしれないと思った時はどのようにしたらいいのでしょうか。
子どもは
痛みや違和感をうまく説明できない
喉の奥をみようとしても協力してもらえない
痛みをがまんできない
大人と違って判断は難しいですし、わが子のことなので親は心配でたまりません。
家ではどう対応したらいいの?
病院を受診したほうがいい?
何科を受診したらいいの?救急?
どうやったら予防できるの?
この記事ではこれらの疑問を解決する方法を説明していきます。
どれぐらい起きているのか
のどや気管に異物が入ったとして耳鼻科を受診した276例の小児例を検討した論文では、36%がのど(咽頭)の異物で、そのうち魚の骨が95%と最も多い原因でした。
魚の種類としてはアジ、ウナギ、サケ、サンマ、サバ、カレイなど一般的な食卓にあがる頻度の多い魚の発生件数が多いです。
咽頭異物を起こす魚の骨の長さは10~15mmで、刺さりやすい場所は口蓋扁桃が50%で、ついで舌根・喉頭蓋谷が30%となります。

佐久間直美 口腔・咽頭の異物としての魚骨に関する研究(1)より引用
喉に骨が刺さったときの症状
- 咳
- 喉の痛み
- 呑み込むときの痛み
- 喉が詰まった感じがする
- 呑み込めない
- 吐血がある
- 発熱、腫れ
軽症から重症まで色々な症状があります。咽頭の粘膜を傷つけただけでも痛みを感じますが、この場合は時間とともに症状は改善します。
太い血管を傷つけた場合は、出血がひどくなるため、吐血を起こすこともあるかもしれません。
発熱、喉周囲の腫れは、骨が刺さった部分に感染が起きると認められる症状です。まれな事例ではありますが報告されています。
これらのうちどの症状があれば病院を受診したらいいのでしょう。そして、救急外来を受診したほうがよい緊急の症状は何でしょうか。
自宅でできること
まずは目で見える範囲に骨がないか確認をしましょう。口をあけてもらい、ライトで照らせば、多くの場合骨は見つけられるはずです。
もし子どもが協力的で、家にピンセットがあるなら骨をとってもいいと思います。しかし、無理だと思った場合は決して触らないでください。骨を押し込んでしまう可能性があります。
骨は自然に抜けることもあるので、何もせず経過観察することも一つの選択肢です。
水でうがいしてみるのも有効な場合があるので、試してもいいと思います。
絶対やってはいけないのは、ごはんなどの食材を呑み込むことです。これは粘膜に浅く刺さった骨であれば、食べ物が通過するときに抜けることもありますが、逆に押し込んでしまう可能性もあるため行わないでください。骨と関係なく、多量の食物で喉を詰まらせるという危険性も伴っています。

病院を受診した方がいいとき
症状が軽いのであれば経過をみても問題ないです。
骨が刺さっていなくても、粘膜が傷ついただけで同じ症状がでることもありますが、その症状は数日で改善していきますから、症状の経過に注意しておけば大丈夫です。
症状が改善しない場合は、骨が刺さっている可能性があるので、病院を受診したほうがいいと考えられます。
その際受診するのは耳鼻科がよいです。
耳鼻科受診が最もよい理由
それは、耳鼻科には処置に必要な器具がそろっている、耳鼻科医は処置の経験が豊富だからです。
喉の奥を観察するためには鼻咽頭・喉頭ファイバー(喉をみるための内視鏡)が必要です。そして骨をとるためには鉗子(かんし)と呼ばれる特殊なピンセットが必要です。これらは小児科にはなく、使用経験もありません。
まずは開業の耳鼻科受診で大丈夫です。
子どもが協力してくれないため麻酔が必要な場合など処置を行うのが難しい場合であれば、小児科が併設された病院へ紹介されることになります。
夜間・時間外救急を受診したほうがいい場合
緊急性があると考えられるのは出血が多いとき、唾を呑み込めないほど痛みが強い場合で、救急外来の受診を検討したほうがいいでしょう。
ただし、救急車が必要な場合はそれほどないと思いますので、地域の救急診療所や#8000へ電話で確認したのちに受診してください。
この時の注意点ですが、救急外来に耳鼻科医が常にいない可能性があるということです。子どもの場合、小児科医や小児外科医が初期対応し、必要に応じて対応可能な病院へ紹介することが多いです。
どのような検査で骨は見つけられるのか?
直接見ることができる鼻咽頭・喉頭ファイバーは、耳鼻科医であればすぐに行える検査で有用です。ただし、深く潜り込んでいる場合などは見つけられない可能性があります。
一般小児科でもできる検査としては、X線画像(レントゲン)がありますが、小骨など小さいな骨であれば映らない可能性があります。
CT検査であれば骨を発見できますし、膿瘍(膿のかたまり)があった場合も見つけることができます。デメリットは放射線の被ばく量がレントゲン検査に比べると多いこと、専門の施設でないとできないことです。
事故を予防する方法
調理の段階で骨を最初から取り除くのが一番よいですが、サンマなど小骨が多い場合はかなり大変です。
骨があらかじめ取り除かれた魚が販売されているので、お子さんや高齢者のいるご家庭では、そのような食材を利用するのが便利です。
成人にサンマを口に入れて咀嚼してもらい、小骨の破砕状況を比較した研究があります。
30回咀嚼すると小骨の長さは10mm以下の破片となり、口の中の食感も気にならず、のどにささることなく飲み込むことができることが判明しました。
50回咀嚼すれば、小骨と身は区別が困難なピューレ状になるそうです。
「よく噛んでたべる」ことは、のどに骨が刺さることを予防してくれます。
まとめ
骨が刺さったと思っても、あわてない
症状がひどいと思ったら早めの耳鼻科受診を
魚の骨を取り除き、よく噛んでたべることが予防です











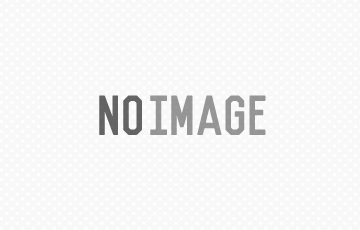


コメントを残す