毎年のように食中毒は起きていますが、家族の食事で何か注意しています?
今まで起こしたことがないから大丈夫という方もいれば
対処法がわからないという方までいると思います。
小さいお子さんがいる家庭では焼肉やBBQは避けた方がいいといわれることがありますが、その理由を知っていますか?
食中毒と、腸管出血性大腸菌で起きる溶血性尿毒症症候群について解説していきます。
食中毒の件数・患者数
厚生労働省の発表では
平成28年 1139件 20252人 死亡者数14人
平成29年 1014件 16464人 死亡者数3人
平成30年 1330件 17282人 死亡者数3人
毎年同程度の食中毒は発生しています。特に夏に多くなります。
原因生物

平成30年の発生状況では第1~3位は以下となります
アニサキス 35.2%
カンピロバクター 24.0%
ノロウイルス 19.2%
大腸菌は3%で、その中でも腸管出血性大腸菌は2.4%となっています。
頻度の少ない大腸菌に、なぜ注意が必要なのでしょうか?
大腸菌が怖い理由
腸管出血性大腸菌が原因で起きる病気が、溶血性尿毒症症候群(HUS)です。
有名なO-157は腸管出血性大腸菌の一つです。
この大腸菌が産生するvero毒素がHUSの原因となります。
O-157感染の9~30%がHUSを発症します。
15歳未満が80%を占めており、その半分が5歳未満です。
HUSとは
経過・症状
通常の細菌性食中毒の潜伏期間が数時間から3日程度であるのに対して、大腸菌によるものは潜伏期間は4~8日と長いのが特徴です。
血便をともなう下痢、嘔吐、腹痛、発熱に引き続き、数日~10日経過してHUSを発症します。
溶血性貧血、血小板減少、急性腎不全の3つを認めれば診断となります。
ICU(集中治療室)へ入院が必要な重症になることがあります。
例えば脳症の場合では、意識障害や昏睡、けいれんをおこすことがあります。
治療・対処法
特別な治療薬があるわけではありません。それぞれの症状・合併症に合わせて治療が行われます。
例えば、けいれんへの対応、腎不全に対して透析、輸血などです。
大腸菌感染源の食品例
井戸水、牛肉、ハンバーグ、ステーキ、サラダ、日本そばなどが報告されています。
動物との接触から感染した事例もあるとのことです。
ヒトからヒトへの感染も注意
感染者の便に大腸菌が含まれているため、直接的・間接的に口から入ることで感染します。
予防するために大事なことは手洗いです。
食事前後は手洗い、アルコール消毒をしましょう。
感染者の便を処理するときも十分に注意が必要です。
菌で汚染されやすい場所を食毒用アルコールで消毒することも大事です。
焼肉、BBQは要注意
親が気を付けて管理すれば問題はありません。
子どもが自分で調理できる年齢のときに注意が必要です。
十分に安全が保てないのであれば、このような食事の方法は避けた方がいいでしょう。
では自宅での食事は何に気を付ければいいのでしょうか。
食中毒予防のポイント
厚生労働省が過程でできる食中毒予防の6つのポイントを紹介しています。
これはHACCP(ハサップ:宇宙食から生まれた衛生管理)と呼ばれています。

ポイント 1 食品の購入
消費期限に注意して新鮮な商品を購入しましょう。
生鮮食品は、購入したら早めに帰宅し、冷蔵庫・冷凍庫へいれましょう。
ポイント 2 家庭での保存
冷蔵庫・冷凍庫などで適切な温度管理をしましょう。
肉、魚の汁が他の食品にかからないような容器がよいです。
肉、魚、卵を扱う前後で手を洗うことも大事です。
ポイント 3 下準備
台所、調理器具などを清潔にしておきましょう。
生肉をあつかった調理器具は使い分けるべきです。生もの用のまな板を使用し、包丁もその都度洗う方がよいです。
井戸水を使用している家庭では、水質に注意してください。
ポイント 4 調理
清潔な器具を使い、食品は十分に加熱しましょう。
めやすは、中心部の温度が75℃で1分間以上加熱することです。
ポイント 5 食事
食事前に手を洗いましょう。清潔な手で、清潔な食器、器具をつかい盛り付けてください。
調理した所持であっても、長時間放置しないようにしましょう。
乳幼児、高齢者は感染した場合症状がひどくなるため、加熱が十分でない食事は食べさせないようにした方が安全です。
ポイント 6 残った食品
適切な容器や温度で保存しましょう。
温めなおすときも十分に、加熱が必要で、めやすは75℃です。
怪しいと思ったら食べずに捨てるようにしてください。
まとめ
十分に加熱することで食中毒は予防できます
子どもの場合、大腸菌感染症が重篤なHUSを起こすことがあります
調理は適切な食材、環境、調理法で行いましょう
以上から子どもとの焼肉、BBQは注意が必要なイベントです











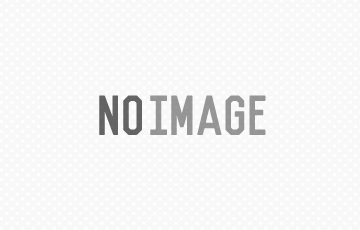


コメントを残す